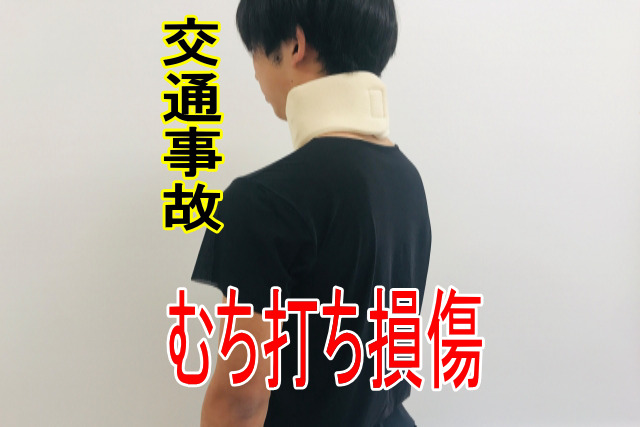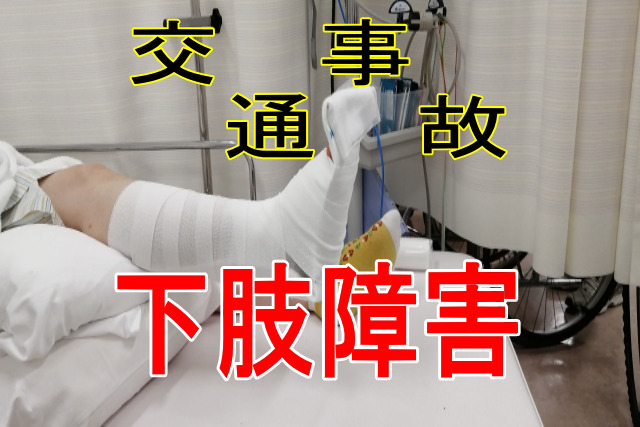これまで多くの方の適正な後遺障害の等級認定を勝ち取ってきた交通事故被害者応援団が取り扱ってきた交通事故による頭部を損傷した事例をもとに、頭部外傷に分類される症状や治療上の注意点についてご紹介いたします。
ご紹介する内容について、深くご理解いただき安心して治療に専念できる一助となれば幸いです。
交通事故による頭部外傷とは?
頭部外傷とは、交通事故による衝撃を受け、頭部に以下の損傷が生じることです。

軟部組織(皮膚、皮下組織)

頭蓋骨

頭蓋内(脳、髄膜など)
頭部外傷は、軽いたんこぶで済むものから頭蓋内において命に係わるほどの大出血にいたるものまで、加わった衝撃の程度によって病態や予後が大きく変わります。
交通事故による頭部外傷には主に以下のものがあります。

びまん性軸索損傷

高次脳機能障害

遷延性意識障害
びまん性軸索損傷
びまん性軸索損傷とは、頭部に外傷を受けたあと意識障害が認められるにも関わらず、頭部CTやMRIで明らかな血腫や脳挫傷などが認められない病態です。
交通事故による強い衝撃を受けた脳に回転力が生じたとき、脳深部は脳表部よりも遅れて回転します。これにより脳はねじれてしまいます。
脳がねじれた結果、軸索と呼ばれる神経細胞体が強く引っ張られます。
強く引っ張られた軸索は広範囲に断裂してしまい、機能を失ってしまいます。
後遺症として、麻痺や意識障害、高次脳機能障害などが考えられます。
高次脳機能障害
交通事故によって脳に外傷を受けたり心肺停止による低酸素脳症などで脳を損傷し、以下のような症状がみられる病態です。

怒りっぽくなった

物覚えが悪くなった

何かにこだわり過ぎるようになった
高次脳機能障害の主な症状
注意障害
注意障害とは、注意力や集中力が低下する障害で、次の症状がみられることがあります。

作業にミスが多くなる

疲れやすくなり長時間作業ができなくなる

気が散りやすいなど、ひとつのことに集中することが難しくなる
記憶障害
記憶障害とは、新たな出来事について覚えられなくなったり、以前のことが思い出せなくなったりする障害で、次の症状がみられることがあります。

約束を守れないまたはすぐ忘れてしまう

物を置いた場所を忘れてしまう

何度も同じ話や質問をする

事実とは異なる話をしてしまう
遂行機能の障害
遂行機能の障害とは、日常生活や仕事の内容を整理・計画・処理するという一連の作業が難しくなる障害で、次の症状がみられることがあります。

行き当たりばったりの行動をする

ひとつひとつ指示されないと行動に移せない

優先順位が決められない

なにかをするときにどこから手をつけていいいのか分からなくなる
社会的行動障害
社会的行動障害とは、感情および行動を自身で調節できなくなってくる障害で、次の症状がみられることがあります。

急に怒りだしたり、泣き出したりする

場違いな場面で、笑い出したりする

気持ちが落ち込みひきこもってしまう

思い通りにならないと興奮して暴力をふるったりする
高次脳機能障害によるこれらの症状は交通事故の直後ではなく退院してから何年も経過した後に現れることもあり家族や友人もしくは同僚など、周囲が気づくことも多いです。
遷延性意識障害
遷延性意識障害とは、交通事故により受けた外傷によってさまざまな治療を受けたにもかかわらず、3か月以上に渡り以下の項目を満たす状態にある病態を指します。

自力で移動できない

自力で食べることができない

大小便を失禁している

目はものを追うが認識はできない

簡単な命令には応ずることもあるがそれ以上の意思の疎通ができない

声は出すが意味のある発語はできない
遷延性意識障害は交通事故の後遺症の中でもきわめて重篤な後遺障害であり被害者の方だけでなく介護するご家族にも多大な苦痛や負担が伴うこととなります。
頭部外傷に関する治療上の注意点
びまん性軸索損傷について、効果的な治療法は発見されていません。
呼吸や循環機能の安定化、高体温防止および頭蓋内圧のコントロールなど、全身管理による二次的脳損傷を予防し脳の回復を期待するよりほかありません。
高次脳機能障害や遷延性意識障害は、治療初期より介護状態の記録を大切に保管する必要があります。
できるだけ以下の内容についてメモに残してください。

病院へお見舞いに行った日付

病院での被害者の様子

医師の発言内容
消毒液やおむつなど、被害者の介護に必要なものについて購入したときは、必ず領収書を保管してください。
自宅介護または病院介護のいずれかの選択については、医師の指示に従ってください。
高次脳機能障害は早期に適切な検査を受けリハビリを開始すれば回復が早いといわれています。
入院している病院が高次脳機能障害を専門に扱っていない場合は、専門的な治療やリハビリを期待できないため、高次脳機能障害のリハビリを専門的におこなっている病院に転院しなければなりません。
入院先の病院によっては、知能検査(神経心理学的検査)をあまり積極的におこなわないところもあります。
後遺障害の等級認定にはこの知能検査の結果が重要視されています。
病院が知能検査に対し積極的ではない場合、別の病院で早期に検査を受けてください。
高次脳機能障害は、事故時の意識消失についても重要視されます。
意識消失の存在を証する資料について多忙な担当医の失念や医師が転勤してしまうことがあるため早期に作成する必要があります。
頭部外傷を立証する画像所見
交通事故による脳の損傷が、画像資料から確認できるかは、後遺障害の等級
認定を判断する重要なポイントです。
脳の損傷を検査する際における主要な検査機器は、以下のとおりです。
CT
X線を照射して得られた断層写真を、コンピュータにより再構築するもの。
骨などの硬い部分における組織を確認するのに適している。
撮影した断層写真について、立体表示させたものをヘリカルCTまたは、
スパイラルCTと呼ぶ。
比較的短時間で撮影できることから、事故直後の頭部画像の撮影にはCTが採用されることが多い。
MRI
磁場の中においた被験者にラジオ波を加え、人体組織を構成する原子核からくる反響信号の強さを画像化します。
体内に磁場をかけ水素イオンに振動を与え、そこが発する共鳴エネルギーをコンピュータ処理して画像化するため水分量が多い軟部組織の抽出に優れています。
MRIを用いた特殊な画像には、次のようなものがあります。

脳脊髄液に接した部分における病変を検索するのに有用とされるFLAIR

脳組織内の水分子の拡散状態を画像化する拡散強調画像(DWI)

MRIで循環画像を作る脳還流画像

ある作業をおこなう際に関連する部分の脳血流量の増加を捉える脳機能MRI

脳出血の跡を検査できるT2スター

T2スターよりもさらに微細な出血痕を捉えるSWI
SPECT・PET
核医学検査のひとつで主として以下の検査が用いられています。

脳の血流量や糖代謝を測定する機能検査

神経線維の脱落を測定する器質的損傷の検査
体内に導入する放射性同位元素の種類により、以下の検査に分かれます。

ガンマ線を用いるSPECT

陽電子を用いるPET
拡散テンソル画像(DWI)
MRIの拡散強調画像(DWI)で得たデータを用いて、脳内の神経線維に沿う水分子の拡散の動きを画像化して神経線維の状態を推定します。
拡散テンソルMRIや拡散テンソルトラクトグラフィなどと呼ばれます。
頭部外傷の立証に有効な神経心理学的検査
人の心理的機能に関する神経心理学的検査は、高次脳機能障害の内容や程度を判断するにあたり重要な参考資料とされています。
心理的機能とは、次の機能を指します。

意識

注意

知能

言語

記憶

視覚・聴覚活動
ただし、脳の状態を知ることのできる神経心理学的検査であっても、障害によっては、いまだ実用化されていないものも存在し完璧とは言えません。
例えば、知能指数は正常で正常範囲であっても、高次脳機能障害が残存することも稀少ではなく、認知機能検査で認知症と判断されなくても障害がないとは言えないとされています。
頭部外傷に有効な神経心理学的検査は大きく次のように分類されます。
脳の全般的な機能に関する検査
脳の全般的な機能に関する検査には、以下のものがあります。
WAIS-Ⅲ
現在、最もよく利用されている脳機能全般を評価するための検査です。
心理アセスメントにおいて用いられる検査バッテリーでは、基本的な検査と位置付けられています。
対象年齢は、16歳から74歳とされています(16歳未満はWISC-Ⅳ)。
検査時の態度から、注意、集中、遂行機能などの障害についても、疑われることがあります。
心理アセスメントとは、複数の知能検査や神経心理学的検査を組み合わせて
結果から、その全体像を把握しようとするアプローチのことをいいます。
検査バッテリーとは、単体では判断し難い心理検査を複数組み合わせること
および組み合された検査全体のことをいいます。
MMS(E)
全世界において汎用されている簡易な認知症検査です。
ミニメンタルステート検査と呼ばれるMMS(E)で行われる検査の内容は次の通りです。

問診や診察などによる病歴や症状の確認

神経心理検査による認知機能の評価

血液検査や画像検査による鑑別診断
11の設問項目で構成されている検査で、満点は30点となっており
健常人は24点以上とされています。
見当識・記憶・計算・言語能力・図形能力について評価されます。
長谷川式知能評価スケール
日本で汎用される簡易的認知用検査です。
9の設問項目で構成されている検査で、満点は30点となっており20点以下は、認知症の疑いがありとされます。
MMS(E)の回答方法が口頭・記述・描画であるのに対し長谷川式知能評価スケールの回答方法は口頭に限られています。
見当識・記憶・計算・言語能力について評価されます。
長谷川式知能評価スケールは、記憶力に重点を置いている点が特徴です。
RCPM
非言語性の認知症検査で、一部が欠如している幾何学的図案の欠如部分に6個の小図案から適当なものを選ぶ検査です。
失語症患者の知能評価に適している。
言語機能に関する検査
言語機能に関する検査には、以下のものがあります。
標準失語症検査(SLTA)・WAB失語症検査
以下の得点パターンにより、失語症の古典的分類が可能となる検査です。

流暢性

理解

復唱

呼称

読み

書き

失行
トークンテスト
形や色、大きさが違うトークン(札)を使い、言語命令に従ってトークンを動かせるかによって聴理解を判断する検査です。
短期記憶の検査として使われることもあります。
視空間認知に関する検査
標準高次視知覚検査(VPTA)
視覚失認・視空間失認について、検出するための検査です。
行為に関する検査
行為に関する検査には、以下のものがあります。
標準高次動作性検査
失行症状について検出するための検査で、13の大項目、45の小項目に分類されています。
大項目の例

観念失行

観念運動失行

肢節運動失行

着衣失行

構成運動失行

運動維持困難など
小項目の例

顔面動作

習慣的動作

手指構成模倣

客体のない動作

連続動作など
Kohs立方体組み合わせテスト
軽度の視覚構成力の障害に関知性能が高い検査です。
色の塗られた複数の立方体を使って見本と同じ模様を作らせるもので、結果がIQに換算されます。
Kohs立方体組み合わせテストの失敗例
モデル
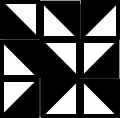
患者による模倣

記憶に関する検査
記憶に関する検査には、以下のものがあります。
WMS-R
世界的に汎用されている記憶検査で、次の評価をおこなうことができるとされます。

視覚性と言語性に分けての評価

即時再生・遅延再生による評価
三宅式記銘検査(東大脳研式記銘検査)
言語性の対連合学習検査で有関係対語(煙草―マッチ等)10対と、無関係対語(水泳―銀行等)10対について記銘力を調べる検査です。
Benton視覚記銘検査
視覚性の記銘検査で、10枚1組の図版を記憶させ、見たとおりに描かせることにより即時再生や保持の能力を検査します。
正解数から全体の脳機能評価を誤謬数から、半側空間無視などの質的評価をおこないます。
Reyの言語性および視覚性記銘検査
視覚性と言語性に分けての評価が可能な記銘力検査です。
視覚性検査では複雑な図形を模写させ遅延再生をおこなう。この図画描画に対して点数が与えられています。
言語性検査では15単語の自由再生を5回させた後、干渉をいれて遅延再生を評価・再認をおこないます。
リバーミード行動記憶検査
日常生活で記憶を使う場面について、シミュレーションして記憶障害を検査します。
前頭葉機能に関する検査
前頭葉機能とは、以下の機能を総称するものです。

概念の転換

ステレオタイプの抑制

複数情報の組織化

流暢性
前頭葉機能に関する検査には、以下のものがあります。
WCST
世界的に最も汎用される前頭葉機能で1組の反応カードを色、形および数の3つの分類基準に基づいて、並べ替えさせていく中で前触れもなく基準を変えた場合に、それを認識できるか、また気づくまで何回誤るかを検査します。
語想起テスト
ある言葉(例えば「う」等)で始まる単語、動物や植物の名前などについて一定時間言わせる検査です。
かなひろいテスト
かなで書かれた短文を読みながら、「あ、い、う、え、お」が出てきたら印をつけると同時に文章の意味理解を問うもので、一度にふたつのことを処理する能力を検査するものです。
か な ひ ろ い テ ス ト
次のかな文の意味を読み取りながら、同時に「あ、い、う、え、お」をひろいあげて、◯を付けて下さい。(制限時間2分間)
むかし あるところに、ひとりぐらしのおばあさんがいて、としを とって、びんぼうでしたが、いつも ほがらかに くらしていました。ちいさなこやに すんでいて、きんじょのひとの つかいはしりを やっては、こちらでひとくち、あちらで ひとのみ、おれいに たべさせてもらって、やっと そのひぐらしを たてていましたが、それでも いつも げんきで ようきで、なにひとつ ふそくはないと いうふうでした。 ところが あるばん、おばあさんが いつものように にこにこしながら、いそいそと うちへ かえるとちゅう、みたばたのみぞのなかに、くろい おおきなつぼをみつけました。「おや、つぼだね。いれるものさえあれば、べんりなものさ。わたしにゃ なにもないが、だれが、このみぞへ おとしていったのかねえ」と、おばあさんは もちぬしが いないかとあたりを みまわしましたが、だれも いません。「おおかた あなが あいたんで、すてたんだろう。そんなら ここに、はなでもいけて、まどにおこう。ちょっくら もっていこうかね」こういって おばあさんはつぼのふたをとって、なかをのぞきました。
BADS(遂行機能障害症候群の行動評価)
次の6つの下位検査と1つの質問紙で構成され様々な検査を組み合わせることにより、遂行機能障害を総合的に判断しようとするものです。

規則返還カード検査

行為計画検査

鍵探し検査

時間判断検査

動物園地図検査

修正6要素
頭部外傷に強い専門家とは
交通事故に関する業務について専門的に取り扱っていない場合、交通事故による遷延性意識障害や高次脳機能障害などの頭部外傷について、詳しくなくても仕方のないことかもしれません。
交通事故を取り扱っている専門家だと謳う者であったとしても、頭部外傷が惹き起こす症状や病態に精通しているとも限りません。
交通事故当初から他覚的所見やあなたが訴える症状をもとに適切な後遺障害の等級認定を見据えた治療法や検査の実施について説明または提案できる者こそが後遺障害を取り扱う専門家だと考えています。
たとえ敏腕弁護士であっても後遺障害非該当となれば、その後の示談交渉や裁判手続きにおいて納得できる結果を導き出すことはとても難しいです。
ウェーブ行政書士事務所団では、あなたの利益を最大限確保するための適正な後遺障害の等級認定の取得を第一の目標としています。
示談交渉や裁判上の手続きがあなたにとって、有利な結果を導くこととなる後遺障害の認定に向け、全力で被害者やそのご家族をサポートいたします。
後遺障害の等級認定申請の代行が完了した後の手続きについては、ウェーブ行政書士事務所の理念に賛同いただいている弁護士があなたを全力でサポートいたします。
ウェーブ行政書士事務所団へご依頼いただいたあなたは、交通事故に関する問題が解決するまでの期間において自身の治療に専念いただくこととなり、示談終了後に必要となる治療費や後遺症による収入減少といった金銭的な不安から解放されることとなります。
.png)