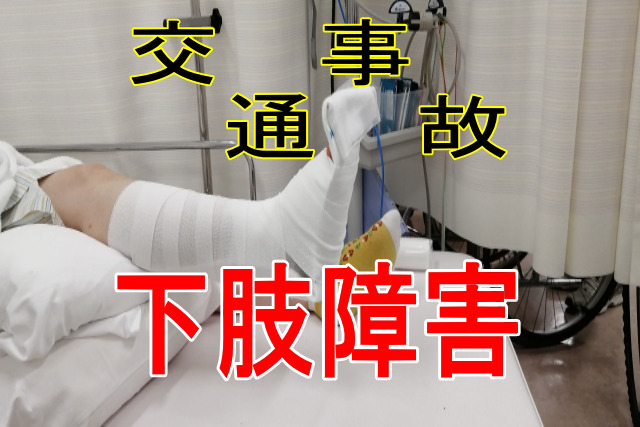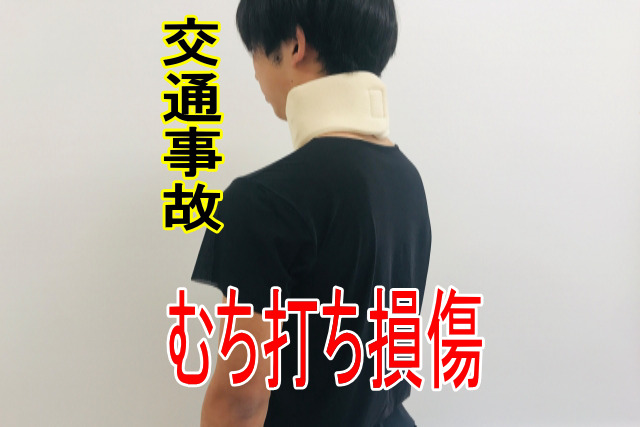これまで多くの方の適正な後遺障害の等級認定を勝ち取ってきた交通事故被害者応援団が取り扱ってきた交通事故によって眼を損傷した事例をもとに、眼の障害に分類される症状や治療上の注意点についてご紹介いたします。
ご紹介する内容について、深くご理解いただき安心して治療に専念できる一助となれば幸いです。
眼の障害とは
交通事故により受傷し、眼周辺への損傷が生じた場合に考えられる障害には、視力障害、運動障・複視、視野障害などがあります。
これらの眼の障害は、交通事故によって単独で生じることはあまりなく、脳の損傷に伴ってあるいは頸椎捻挫等とともに主張されることの多い障害です。
眼の障害には、主に視力が低下や失明などの眼球障害、まぶたを完全に閉じることができなくなるといったまぶたの障害などがあります。
複視とは、それぞれの眼球が同じ方に向かないために、外界の像が左右眼の対応点でない部位に投影されて二重に見える状態のことです。
人の日常生活の動作において欠かせない組織である眼が交通事故により損傷した場合、日常生活および労働に支障をきたすことから賠償の対象となっています。
眼の障害における治療
医師による診断
交通事故の後、目がよく見えないと感じたときやまぶたを閉じることができなくなったときは、速やかに医師による診断および治療を受けてください。
交通事故現場では動揺しているため気付かないこともありますが、どんな些細なことでも身体に異変を感じるときは救急車を利用し、至急、病院へ向かい受診することをお勧めいたします。
救急搬送された事実の有無が、後遺障害の等級認定を判断する際において大きく影響することがあります。
交通事故が発生した直後に病院へ行かず、交通事故から数日経過した後に病院へ向かっても、その痛みが交通事故によるものなのか、それとも他の原因によるものなのかが不明となります。
原因が解明できない痛みについて、相手方の保険会社が治療費や慰謝料を支払うことはありません。
それどころか、交通事故との因果関係を否定し交通事故による損傷ではないことを主張してくることが考えられます。
診断時に注意すること
交通事故によって生じた視力低下や複視などの症状を医師に伝えるときは、できるだけ正確に伝えてください。
医師は、初期の症状として患者の主張をカルテに記載します。
症状について、伝え忘れがあったまたはうまく伝わっていなかった場合、当然、その内容についてカルテに記載されることはなく、交通事故発生時にその症状はなかったものとして扱われます。
そうなると、後発した痛みやしびれなどの症状については交通事故によって発生したか不明となり、後遺障害の等級が認定されないまたは認定されても不本意な認定となることがあります。
検査の実施
病院での受診後、数日経っても症状が治まらないときは、早期に後述する検査を実施してください。
医師へ交通事故による眼周辺の異常を伝えたとき、必ずと言っていいほどの確率で視力検査は実施されますが、他の検査はあまり実施されません。
眼周辺の損傷について存在する8種類の検査をそれぞれ実施することで、損傷した部位の状態を確実に知ることができることも少なくありません。
通院している病院に各検査の設備がなくても、医師に伝えると紹介状を作成してくれるため、紹介状記載の病院でそれぞれの検査を受けることができます
通院期間中
交通事故により損傷した部位およびその周辺に継続して症状がある場合、医師により指示されて治療または診察を受けてください。
医師による診察は通院する度に受診する必要はなく、2週間や1カ月に1回程度でも構いません。
医師より診察日について指示を受けている場合、それに従って受診してください。
交通事故によるケガに対しておこなわれる治療は、週に3回~4回受けることをお勧めしています。
治療または診察の頻度は、症状が最も強い交通事故直後が高くなり、時間の経過とともに低くなっていくものだと考えられています。
明確な基準の公表はありませんが、通院回数が極端に少ないまたは通院期間中に2週間以上治療を受けていない期間があるなどに該当すれば、後遺障害が認定されることはほとんどありません。
鍼灸院への通院や温泉などの利用
交通事故により損傷を受けた部位を治療するため、鍼灸院への通院や温泉などを利用すること自体は問題ありません。
ただし、後遺障害と認定されるためには、原則として医師が在籍する病院への一定程度の通院が要件とされています。
最高裁判所は判例で、整骨院および接骨院等による交通事故の治療が例外的に通院と認められるのは次のいずれかに限ると明示しています。

医師の指示がある場合

症状により有効かつ相当と認められる場合
病院と並行して鍼灸院や温泉等を利用すること自体は構わないですが、病院への通院実績と混同してしまった場合、通院回数の不足を理由に後遺障害と認定されなくなることがあります。
眼の障害と後遺障害
症状固定
医師から症状固定予定日を告げられたら、後遺障害診断書を作成する準備を始めます。
症状固定とは、そのまま治療を継続しても著しい改善が見込めなくなった状態のことです。
【注意】症状固定日は医師が決めるもので、保険会社が独自に決定して医師に定めるよう指図するものではありません。
眼の障害における後遺障害診断書には、医師の所見または視力検査および電気生理学的検査などの結果を記載してもらいます。
完成した後遺障害診断書は、被害者請求と呼ばれる方法で自賠責保険会社に提出し、後遺障害の等級認定を申請します。
交通事故被害者応援団へご依頼いただいた場合、症状固定日以降の後遺障害診断時におこなわれる検査に同行し、適切な後遺障害等級認定に向けた後遺障害診断書の作成を医師に指示いたします。
交通事故発生直後から症状固定日を迎えるまで準備してきた数々の資料に加え、症状固定日時点のお客さまの主張および身体の状況についての意見書を添付し、後遺障害の等級認定申請を代行いたします。
眼の障害で認定される後遺障害の等級
眼の障害における後遺症は、後遺障害等級表に認定基準が明示されてるものと後遺障害等級表に認定基準の明示はありませんが、認定基準に準じる相当等級に該当するものとして認定される症状が存在しています。
後遺障害等級表に明示されている症状には、眼球障害とまぶたの障害があります。
相当等級に該当するものとして認定される症状には、外傷性散瞳、流涙があります。
眼球は、左右の両器官をもってひとつの機能を担う相対性器官としての特質から、両眼球でひとつの部位とされています。
眼球障害
後遺障害と認定される眼球障害には次のものがあります。
視力障害の認定基準
視力障害の後遺障害の認定基準は、次のように定められています。
| 等 級 | 障害の程度 |
| 1級1号 | 両眼が失明したもの |
| 2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
| 3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
| 4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
| 5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
| 6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
| 7級3号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
| 8級1号 | 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの |
| 9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
| 9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
| 10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
| 13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
視力
視力とは、2点を識別する眼の能力をいい、基本的には2点または2線を認識できる閾値で示されますが、実際には離れている2点を見分ける1番小さな角度(最小分離閾)のことで、視力の値はその逆数であらわされるものです。
後遺障害等級表の「視力」とは、矯正視力のことを指し万国式試視力表をもとに判断されます。
矯正視力には、眼鏡による強制と1日に連続8時間以上連続して装用で市視力きるコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正が含まれます。
眼内レンズとは、手術などにより水晶体を摘出したときに挿入される人口の水晶体のことで、丸いレンズ本体とレンズを固定する2本の支持部で構成されています。
視力は原則として、万国式試視力表により測定されますが、例外的に、これと同等程度と認められる文字や図形等の指標を用いた試視力表または視力測定法の利用が認められることもあります。
失明
失明とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないものおよびようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)または手動弁が含まれます。
光覚弁(明暗弁)とは、暗室にて被験者の眼前で証明を点滅させて明暗が区別できる視力のことをいいます。
手動弁とは、検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を区別できる能力のことをいいます。
両眼に障害が生じた場合
両眼の視力障害について、後遺障害等級表が掲げる両眼の視力障害の該当する等級をもって認定されるとし、1眼ごとの等級をもって併合繰上げの方法を用いる相当等級は採用しないと定められています。
ただし、両眼の該当する等級よりもいずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が残存するものとみなして等級が認定されます。
眼球に2つ以上障害がある場合
眼球に異なる系列の2つ以上の後遺障害が残った場合、同一系列として取り扱い、原則として併合の方法により相当等級を定めることとなります。
ただし、後遺障害の序列上1眼について失明(8級)を超えて7級相当と取り扱うことはできず、両眼の場合にも視力が保たれている限り、併合の方法により1級相当と取り扱うことはできません。
調節機能障害の認定基準
調節機能障害の後遺障害の認定基準は、次のように定められています。
| 等 級 | 障害の程度 |
| 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
| 2級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
調節
眼球の調節とは、眼に近い物体を見る場合、毛様体筋の作用によって水晶体の厚みを変化させ、その物体から届いた光線が適当に屈折されて網膜に像を映し出す運動をいいます。
眼の調節を休止した状態で、遠方から届く平行な光線が角膜、眼房水、水晶体、硝子体を通過して網膜面に像を映し出すものを正視といい、網膜面より前方に像を映し出すものを近視、後方に映し出すものを遠視と言います。
調節力とは、遠点から近点までのピントが合う距離的な範囲(調節域)をレンズに換算した値のことで、単位はジオプトリ―(D)で表します。
遠点とは、眼が調節をしていないときに明視できる点のことをいい、最大に調節したときに明視できる最も近い点を近点といいます。
眼球に著しい障害を残すものとは、調節力が通常の場合の2分の1以下に減少することをいいます。
2分の1以下な該当するか否かは、損傷した眼が1眼の場合は、受傷していない他眼との比較により判断され、両眼を損傷した場合および損傷した眼は1眼であるが受傷していない他眼の調節力に異常が認められる場合は、年齢別の調節力値と比較して判断されます。
5年ごとの年齢に応じた調節力
| 年 齢 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 調節力 | 9.7 | 9.0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.35 | 1.3 |
運動機能障害の認定基準
運動機能障害の後遺障害の認定基準は、次のように定められています。
| 等 級 | 障害の程度 |
| 10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
| 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| 12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
| 13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
眼球の運動
眼球は、各眼3対、左右合わせて6つの外眼筋の作用により運動しています。
この6つの外眼筋は、それぞれ一定の緊張を保つことで眼球の位置が正常なものとなるよう働いています。
仮に外眼筋のうち、1つあるいは複数が麻痺した場合、眼球は麻痺した筋の反対の方向へかたより(麻痺性斜視)、麻痺した筋の働くべき方向において眼球の運動が制限されることとなります。
眼球に著しい運動障害を残すものとは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減少したものをいいます。
注視野とは、頭部を固定した状態で眼球を運動させて直視することのできる範囲のことです。
両眼の眼球に著しい運動障害を残すものとは、単眼視での注視野の広さが左右両眼とも2分の1以下に減少したもののことで、両眼視での注視野の広さが2分の1以下に減少したものではないことに注意してください。
複視
後遺障害の等級認定基準において「複視を残すもの」といえるためには、次の要件をすべて満たすことが必要となります。

本人が複視であることを自覚していること

眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること

患者の像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れていること
この要件を満たすもののうち「正面視で複視を残すもの」とは、ヘス赤緑テストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいい、それ以外のものを「正面視以外で複視を残すもの」といいます。
そのほかの複視
①開散麻痺
開散とは、両眼が眼前の近くの1点を注視した状態から水平に遠方の対象に眼転ずる際に眼球が分散する動きのことで、外よせともいいます。
開散の反対の両眼の動きを輻輳(ふくそう)または内よせといいます。
②輻輳痙攣
輻輳とは、近距離にある1点を注視するとき、両眼の視線は注視点で交差する機能のことです。
輻輳痙攣とは、発作性または持続性に輻輳が過剰となり、両眼が内転し遠方視で同側性複視を訴え、調節痙攣と縮瞳を伴うものをいいますが、大部分が心因性によるもので自然軽快することが多いです。
③単眼性複視
片眼で見た対象物が二重に見える症状で、近視、遠視、乱視などの屈折異常により起こる場合と、水晶体亜脱臼や眼内レンズ偏位などにより起こる場合とがあり、視力障害として判断されています。
視野障害の認定基準
視野障害の後遺障害の認定基準は、次のように定められています。
| 等 級 | 障害の程度 |
| 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
| 13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
視野
視野とは、眼前の一点を見つめていて、同時に見ることができる外界の広さのことをいいます。
視野は、動的量的視野計測に用いられるゴールドマン視野計によって測定されます。
視野障害
視野障害の種類には、次のものがあります。
半盲症
半盲症とは、視神経線維が、視神経交叉またはそれより後方に置いておかされるときに生じるもので、注視点を境界として、両眼の視野の右半部または左半部が欠損するものをいいます。
両眼の同じ側が欠損するものを同側半盲または同名半盲と呼び、右と左とでは反対側が見えなくなるものを異名半盲と呼びます。
また、両側の眼の一致した4分の1が見えなくなる4分の1半盲または四半盲などがあります。
視野狭窄
視野狭窄とは、視野周辺の狭窄であり、8方向ある指標による視野の合計角度が336度(正常視野の60%)以下になったものをいい、同心性狭窄と不規則狭窄があります。
同心性狭窄とは、視野全体が狭くなることで、求心性狭窄とも呼ばれるものです。
不規則狭窄とは、視野が不規則に狭くなることです。
視野変状
視野変状は、半盲症、視野の欠損、視野狭窄および暗転が含みますが、半盲症および視野狭窄については後遺障害等級表に明示されているため、狭義の視野変状についてご紹介いたします。
視野の欠損とは、網膜に感受できない部分が発生したことにより、視野上に欠損が生じることで、生理的に存在するものと病的に発生するものがあります。
暗転とは、中心正漿液性脈絡網膜炎、網膜の出血、脈絡網膜炎などの症状に見られることの多い生理的視野欠損以外の病的欠損を生じたもののことです。
まぶたの障害
後遺障害と認定されるまぶたの障害は次の2つがあります。
欠損障害
| 等 級 | 障害の程度 |
| 9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
| 14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
まぶたに著しい欠損を残すものとは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができない程度のことをいいます。
まぶたの一部に欠損を残すものとは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことはできるが、球結膜(白目)が露出している程度のことをいいます。
まつげはげを残すものとは、まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
運動障害
まぶたの運動は、開瞼は上眼瞼を持ち上げる上眼瞼挙筋(動眼神経)と瞼裂を開大する上下の瞼板筋(交感神経)により、閉瞼は瞼裂を閉じる眼輪筋(顔面神経)によって、それぞれおこなわれます。
| 等 級 | 障害の程度 |
| 11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
| 12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
まぶたに著しい運動障害を残すものとは、開瞼時に瞳孔領を完全に覆うものまた閉瞼時に角膜を完全に覆うことのできないものをいいます。
眼瞼が完全に閉瞼せず、常に眼球の一部が露出している状態のことを兎眼(とがん)といいます。
外傷性散瞳
病的な散瞳(さんどう)とは、瞳孔の直径が開大して対光反応が消失または減弱するものをいい、次の基準により相当等級が認定されます。
| 相当等級 | 症 状 |
| 11級相当 | 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
| 12級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
| 13級相当 | 両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |
| 14級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |
| 併 合 | 外傷性散瞳と視野障害または調節機能障害が損する場合 |
羞明とは、正常であれば、通常何も感じない光をまぶしいと感じる状態のことをいいます。
流涙
涙(液)は、上円蓋部耳側の涙腺開口部より分泌され一部は蒸発しますが、大部分は大部分は上下眼瞼内側にある涙点から涙小管、涙嚢、鼻涙管を経て下鼻道に流出し、この経路のことを涙道といいます。
流涙とは、眼表面の涙液量が、過剰に増加した状態のことをいいます。
流涙の原因として、涙液の分泌量が過剰である場合と涙液の排出器官が損傷している場合とがあり、涙道が交通事故などの外傷を受けたことにより断裂、狭窄もしくは閉塞した場合、流涙が生じます。
| 相当等級 | 症 状 |
| 12級相当 | 両眼に流涙が残ったもの |
| 14級相当 | 1眼に流涙が残ったもの |
眼の障害を立証する検査
自賠責保険に後遺障害と認定されるため必要となる検査は、大きく次のように分類されています。
視力検査
視力検査は自覚的なものまたは他覚的なものに分かれています。
自覚的な視力検査
遠見視力検査
一般的な視力検査としてなじみ深く、検査距離5mの位置から片眼を遮蔽し、ランドルト環が記載されている視力表の指標の上から順次指し示して環の開いている方向を答える検査です。
指標が5列並んでいる場合には、3個以上判別できればその段の視力とされます。
他覚的な視力検査
主な他覚的視力検査には、次のものがあります。
テラーアキュイティカード検査
テラーアキュイティカード検査とは、片側半分に白黒コントラストの縞模様が描かれ中央に直径約4mmの小さな穴が開いたカードの穴から検者(医師等)が被験者(患者)の眼の動きを観察するものです。
テラーアキュイティカードは、ワシントン大学のテラー博士およびその研究チームにより開発された、乳幼児や言葉を発することが不自由な被験者用の他覚的視力検査カードです。
視運動性眼振検査
眼振とは、眼球振盪を省略した呼び方で、本人の意思とは関係なく眼球が痙攣したように動いたり揺れたりすることです。
移動している自動車や電車の車窓から、見るともなしに周囲の風景を眺めているとき、眼球は流れる風景を負う遅い運動とそれをリセットする逆向きの早い運動を繰り返しています。
この繰り返されている眼球の運動を視(覚性)運動性眼振と呼びます。
視(覚性)運動性眼振検査は、脳幹や小脳における疾患の診断に優れる視運動性眼振開発装置を用いる検査です。
視運動性眼振抑制検査
視(覚性)運動性眼振検査および視運動性眼振抑制検査では、瞬きによってエラーが発生し、それが検査結果に反映されてしまうことに注意しなければなりません。
視覚誘発電位検査
視覚誘発電位検査とは、視覚刺激を与えることで大脳皮質視覚野に生じる電位を計測し、視神経以降より脳までの働きを調べる検査で、脱髄、中毒、圧迫、虚血などの視神経病変を判断する際に用いられるものです。
調節機能検査
調節機能検査は、次の症状を対象に調節近点や調節遠点、調節力および調節時間などを測定します。

調節異常をきたす疾患

遠視や老視

神経眼科的疾患が疑われるもの

弱視

斜視

眼精疲労や近見障害の自覚症状を有するもの
主な調節機能検査には、次のものがあります。
近点距離計検査
近点距離計検査とは、調節機能障害が疑われる場合に調節の近点がどの位置にあるかを知るための検査で、調節力を調節遠点から調節近点までのジオプトリ―(D)の変化幅として求めるものです。
石原式近点計と呼ばれる検査機器を用いて近点、遠点を測定して調節力を算出します。
近点距離計検査による調節力検査は、自覚的調節検査に含まれます。
アコモドポリレコーダー
アコモドポリレコーダーとは、遠方と近方におかれた視標にピントが合うまでの時間の長さから調節機能障害を診断する装置のことで、内蔵されている視標はレンズによって光学的に遠方と近方に設置され、電動式に遠方指標と近方標示が交互に点灯するようになっています。
アコモドポリレコーダーによる調節力検査は、自覚的調節検査に含まれます。
アコモドメータ(赤外線オプトメータ)
アコモドメータは、視標を動かしながら検査する動的測定方法と、視標を眼の前から一定の距離において、これを注視させたときの屈折変動を測定する静的測定方法に対応するものです。
アコモドメータを用いた調節機能検査は、他覚的調節機能検査に含まれます。
視野検査
視野検査には、次のように分類されています。
対坐によるもの
対座法
検者(医師など)と被験者(患者)とが向かい合って座り、片方の眼を眼帯などでふさいだ状態で互いに相対した眼球を注視しながら、検者が指やペンなどの指標を周辺から移動し、検者自身の視野と被験者の視野を比較する検査方法です。
当然、検者自身が正常な視野の持ち主であることが求められますが、たいていの周辺視野を測定する際に用いられる方法です。
動的な視野検査
ゴールドマン視野計
視力不良や固視不良、周辺部異常が疑われるとき、頭蓋内病変の局在診断や広がりの判定をするときには自動視野計を用いるより適しているとされています。
自賠責における認定では、視野障害の測定はこれを用いるものとされています。
静的な視野検査
静的な視野検査は、主に次のものがあります。
ハンフリー検査
疾患に特有な視野以上のパターンの検出と以上の程度の把握、視機能の評価およびそれらの経時的変化の追跡による経過観察を目的とするもので、自覚的調節検査に含まれます。
視路疾患のうち、次の疾患に対応する検査をおこないます。

神経疾患では診断のための特異的な視野異常の検出と経過観察

中枢疾患では病巣の城への影響の程度を知る
アムスラーチャート
黄斑疾患の初期の機能障害を分析することを目的とする中心暗転検査で、質的な視野障害が検出できるため、次の症状について捕えることができます。

破線現象

変視
破線現象とは、ぷつぷつと線が途切れて見える現象のことです。
変視とは、線がグニャグニャと曲がって見える現象のことです。
フリッカ視野計
光が点いたり消えたりする不連続光を見るとちらつきを感じ、この頻度が高くなっていくと遂には融合してちらつきを感じられなくなる時の時間的な分解能力を各疾患において測定するもので、緑内障、視神経疾患、視路疾患を検査対象としています、
眼振検査
眼振の状態を他覚的に測定・記録し、波形を詳細に解析することによって眼振の種類や程度を把握し、確定診断のための補助診断のひとつで、主に次のものがあります。
電気眼振計/直流眼球運動記録法
電気眼振計とは、眼球の左右の皮膚に電極を貼り、眼球運動により発生した電位変動を拾い、記録する検査です。
光電素子眼球運動記録法/赤外線輪部(角膜)反射法
光電素子眼球運動記録法とは、赤外線を角膜と強膜にあて、その反射光の入力差から眼球運動を検出する方法です。
サーチコイル法
サーチコイルとは、眼球にサーチコイル(測温抵抗体)を装着し、眼球運動に伴って発生する電流を記録して、眼球運動を測定する方法です。
眼位・眼球運動検査
眼位とは、左右の眼の見ている方向のことをいい、眼位の異常には斜位や斜視があります。
斜位とは、遠方あるいは近方において、両眼で対象物を見ている際に片側の眼を隠すと、隠された眼の視線の向きが上下や左右にずれて対象物に向いていない状態をいいます。
斜視とは、片方の眼が見ようとするものを見ているにもかかわらず、もう片方の眼が目標と違う方向へ向いている状態です。
眼位・眼球運動の検査には、ヘス赤緑テストが採用されています。
ヘス赤緑テスト
斜視、眼球運動障害、複視や頭位異常を示す者を対象として、指標を赤緑眼鏡(ガラス)で見たときの片眼の赤像、もう片方の眼の緑像から眼位異常の程度やパターンなど、両眼の位置ずれを測定・評価する検査です。
暗室で縦横に碁盤の目のような線が引いてある黒板のようなもの(ヘススクリーン)を使用し、片眼が緑色、残りの片眼が赤色の眼鏡をかけてヘススクリーン上に点いた赤い光に緑に光るライトを動かして重ね合わせることからヘススクリーンテストとも呼ばれます。
頭位異常とは、上下や側方の目標物を注視するときに横目づかい、上目づかいおよび下目づかいあるいは顔を傾げた状態をとることをいいます。
眼底検査
眼の疾患のうち、網膜ならびに脈絡膜疾患の病像を直接観察する重要な基本的眼科的検査とされる主な眼底検査法には、次のものがあります。
倒像検眼鏡による検査
倒像顕微鏡による検査とは、取り扱いに習熟した眼科医が専門的に使用する倒像顕微鏡によりおこなわれるもので、一視野で見える範囲が広いことから拡大倍率を大きくする必要のない検査に優れているとされています。
細隙灯顕微鏡による検査
細隙灯顕微鏡による検査とは、細隙灯(さいげきとう)と呼ばれる拡大鏡により帯状の光を目に当てる検査で、結膜、角膜、前房水、虹彩、瞳孔、水晶体などが検査でき、眼科では診察のたびにおこなわれるものです。
また、特殊なレンズを用いれば後眼部の硝子体や網膜の状態まで検査できます。
直像鏡による検査
直像鏡による検査とは、直像鏡(眼底鏡)を用いて直接、眼底部を観察して眼底部の異常を発見する検査で、網膜剥離、緑内障、黄斑部変性などを測定するものです。
電気生理学的検査
光刺激を受けたり、対象物を見たりした際に、網膜、視神経および大脳に発生する電位を調べる検査で、主に次のものがあります。
ERG検査(網膜電図)
閃光に対する網膜の反応を計測し、それにより網膜の視細胞の機能を調べる検査です。
網膜にある程度広範囲な機能障害があると疑われるときにおこなわれます。
VEP検査(視覚誘発電位検査)
VEPは視覚への刺激に対する大脳皮質の活動の信号を記録する検査で、主に黄斑疾患や視神経疾患などの異常所見を測定するものです。
EOG検査(眼球電図)
眼運動神経麻痺、核上性眼球運動障害、機械的眼球運動障害、眼振などの自発性異常眼球運動に加え斜視などの眼位・眼球運動障害が検査対象です。
眼球には、角膜側が(+)網膜側が(-)となる常在電位が存在していますが、眼球周囲に貼った電極に角膜側が接近したとき(+)に振れる電位を連続的に記録する検査です。
瞳孔検査
眼底検査に含まれることの多い瞳孔検査には、交互点滅対光反射試験が採用されています。
交互点滅対光反射試験
視神経または中心部網膜の障害を対象としているもので、患者の眼の下方からペンライトなどで左右眼に交互に光照射を素早く繰り返し、両眼の動向の大きさの変化をみるテストです。
1個の視神経または中心部網膜に障害があれば、患側の瞳孔が大きくなった状態(散瞳)となります。
眼の障害に詳しい専門家とは
交通事故に関する業務について専門的に取り扱っていない場合、交通事故による視力障害などの眼球障害やまぶたの運動障害などの眼の障害について、詳しくなくても仕方のないことかもしれません。
交通事故を取り扱っている専門家だと謳う者であったとしても、眼の障害が惹き起こす症状や病態に精通しているとも限りません。
交通事故当初から他覚的所見やあなたが訴える症状をもとに適切な後遺障害の等級認定を見据えた治療法や検査の実施について説明または提案できる者こそが後遺障害を取り扱う専門家だと考えています。
たとえ敏腕弁護士であっても後遺障害非該当となれば、その後の示談交渉や裁判手続きにおいて納得できる結果を導き出すことはとても難しいです。
ウェーブ行政書士事務所では、あなたの利益を最大限確保するための適正な後遺障害の等級認定の取得を第一の目標としています。
示談交渉や裁判上の手続きがあなたにとって、有利な結果を導くこととなる後遺障害の認定に向け、全力で被害者やそのご家族をサポートいたします。
後遺障害の等級認定申請の代行が完了した後の手続きについては、ウェーブ行政書士事務所の理念に賛同いただいている弁護士があなたを全力でサポートいたします。
ウェーブ行政書士事務所へご依頼いただいたあなたは、交通事故に関する問題が解決するまでの期間において自身の治療に専念いただくこととなり、示談終了後に必要となる治療費や後遺症による収入減少といった金銭的な不安から解放されることとなります。
.png)