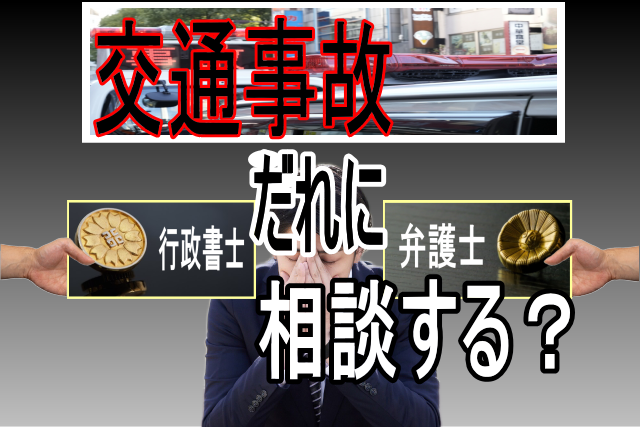突然発生した交通事故により負傷することは誰にでも起こり得る身近な問題となりました。
交通事故が発生したとき、自動車を運転する者がすべきことについて道路交通法に定められていますが、運転免許を取得した直後は覚えていても時間の経過や交通事故に遭遇しなかったことなどを理由に、忘れてしまうことがあります。
人身事故が発生した直後から交通事故処理が終了するまでの間において、当事者がしなければならないこと、すべきことおよび絶対にしてはならないことについて説明いたします。
現在交通事故の当事者となっていない方においても、突然発生する交通事故に備え常に冷静に判断および対処できる一助となれば幸いです。
人身事故発生!
人身事故の発生により突然「交通事故の当事者」となってしまうことから、冷静な自分を保つことのできないことが多いですが、自身が被害者・加害者のそれぞれの立場となったとき、どれだけ冷静に対応できるかによって結果が大きく変わることがあるため、注意が必要です。
交通事故の加害者と被害者
日常生活を送るうえで、車やバイクなどの交通手段や自身が運転していたか否かなどを問わず、交通事故の当事者となる可能性があります。
また、交通事故の当事者は相手(複数の場合も含みます)との関係において、加害者または被害者のいずれかの立場となります。
交通事故における加害者と被害者は、それぞれ以下のように分類されます。
過失割合による加害者と被害者
過失割合によって分類される加害者と被害者について解説する前に、少しだけ過失割合について説明いたします。
過失割合とは、交通事故を起こした当事者同士の過失の割合を過去の裁判例を基準に導き出す数値のことです。
過失割合は、交通事故現場において警察官によって決定されるものではなく、示談交渉によって決定されます。
過失とは、自身の行為によって一定の結果が生じるといった認識があり、その結果が生じることを回避することが可能であったにもかかわらず、回避するための行動を怠った不注意のことです。
携帯電話等の操作のため脇見していた、悩み事などを漫然と考えていた、道路標識を見落としていたなど、自身の不注意により交通事故を惹き起こした割合が高ければ加害者となります。
自身は細心の注意を払って運転していたが、信号を無視した車両に衝突されたなど、不注意の割合が低いときは被害者となります。
加害者と被害者の過失の割合に応じて交通事故の当事車両の修理代を支払う割合や慰謝料の支配額が変動します。
過失割合による加害者と被害者とは、交通事故が発生した際に一般的に分類される加害者と被害者のことを指します。
負傷状況による加害者と被害者
負傷状況によって分類される加害者と被害者とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)における概念で、交通事故の相手を負傷させたか交通事故の相手から負傷させられたかによって分類されます。
自賠法では、交通事故によって相手を負傷させた者を加害者とし、相手から負傷させられた者を被害者と考えられます。
刑事上または民事上における加害者および被害者のように違法性や過失の割合で判断されるものではありません。
交通事故のすべての当事者が相手を負傷させた場合はすべての者が加害者となり、すべての当事者が負傷している場合はすべての者が被害者となります。
交通事故の相手を負傷させ、自身も負傷している場合には加害者・被害者両方の立場となります。
交通事故の当事者に課せられる義務
人身事故が発生したとき、自動車を運転していた者に課せられる義務は以下のとおりです。
ただし、自動車を運転していた者が意識不明の場合や、病院へ緊急搬送しなければ生命に支障のある場合などはこの限りではありません。
負傷者の救護、救急車の手配
交通事故の発生により負傷した者がいるときは、自身が交通事故の被害者または加害者であるかにかかわらず、その負傷者を救護することが最優先事項となります。
負傷者には、交通事故の当事者・第三者について区別されていないため、当該事故の発生により受傷したすべての者が含まれます。
例えば
交差点を直進している自動車と対抗する右折車が接触した衝撃により、右折車両が横断歩道付近で信号待ちをしている歩行者と接触してその歩行者が負傷した場合における歩行者についても、当該交通事故による負傷者となります。
交通事故により負傷した者がいる場合、負傷の程度にかかわらず救急車を手配します。
負傷者が軽傷の場合、他の交通が通行しない歩道や空き地、駐車場などの安全なところへ非難してもらい、救急車の到着を待ちます。
負傷者が頭部に強い衝撃を受けているまたは負傷者の意識がないなどの重傷の場合、負傷者を動かさず救急車の到着を待ちます。
負傷者を動かすことができないときは、警察官が交通事故現場へ到着するまでの間、他の交通と負傷者が接触する二次的被害の発生を防ぐため、他の交通を誘導するよう努めなければなりません。
事故車両の運転禁止
交通事故現場では、次のような特段の事情のないときは事故車両を運転することはできません。
 自動車の下敷きになっている負傷者を救護する必要があるとき
自動車の下敷きになっている負傷者を救護する必要があるとき 事故車両が周囲の交通を妨げており、二次的な交通事故を発生させてしまう危険を除く必要があるとき
事故車両が周囲の交通を妨げており、二次的な交通事故を発生させてしまう危険を除く必要があるとき 警察官の指示によるとき
警察官の指示によるとき
警察へ連絡(110番通報)
交通事故の当事者は、その規模の大小や人身事故・物損事故などの形態にかかわらず、交通事故が発生したときには直ちに警察に報告をしなければならず、これに違反すると罰せられます。
通報したときに警察へ伝える内容は、住所や交差点名など交通事故が発生した場所、交通事故発生時刻、通報者の氏名、けが人の有無、簡単な交通事故態様などです。
通報時に簡単な交通事故態様を伝える理由は、交通事故により交差点を封鎖している場合や死亡した者がいる場合など、交通事故の態様に応じて交通事故現場へ警察官を派遣する人数をあらかじめ判断する必要があるためです。
110番通報した際、警察官から質問される内容に対し、確実に回答できるよう落ち着いて対応してください。
危険防止措置
二次的な交通事故の発生を避けるため、事故車両を道路脇など他の交通の支障とならない場所へ移動し、ハザードランプや発炎筒などを用いて後続車に知らせるようにし、必要な場合は他の交通を誘導します。
警察官へ交通事故が発生した状況を報告するため交通事故現場を維持しなければならないと認識を誤っている方をお見受けいたしますが、交通事故が発生した状況をそのまま保全する義務は存在せず、危険防止措置のため事故車両を移動しても過失割合などへの影響は少ないため、事故車両の移動が可能であるときは、他の交通への影響が少ない場所へ事故車両を移動しなければなりません。
交通事故の当事者がすべきこと
人身事故が発生したとき、自動車を運転していた者がすべきことは以下のとおりです。
ただし、自動車を運転していた者が意識不明の場合や、病院へ緊急搬送しなければ生命に支障のある場合などはこの限りではありません。
相手方の連絡先を確認
交通事故の当事者となったときは、必ず以下の交通事故の相手に関する情報について、免許証や身分証明書、名刺などを確認しメモ用紙または写真に収めてください。
 住んでいる所※1
住んでいる所※1 氏名
氏名 電話番号※2
電話番号※2 勤務先名
勤務先名 勤務先の電話番号
勤務先の電話番号
※1 免許証の表面に記載されている住所と現に生活を送っている所(居所)が異なることがあります。必ず確認してください。
※2 通常連絡できる電話番号であれば、固定電話や携帯電話を問いません。
交通事故現場において当該交通事故について目撃していた者がいる場合、後日、警察官等へ交通事故が発生した状況について証言してもらう旨を伝え、目撃者から連絡先を伺っておくことをお勧めします。
車両損傷個所の確認
交通事故の相手が運転していた車両に備えられている車検証に記載されている番号と車両のナンバープレートが一致していることを確認した後、番号をメモ用紙や写真に収めてください。
可能であれば、携帯電話のカメラ等を用いて自分の車と相手の車の被害状況や事故現場が判別出来るよう、他の交通に十分注意してさまざまな角度からたくさん写真を撮影してください。
これは、交通事故とは関係のない損傷箇所における修復を要求されることを防ぐ、または時間の経過とともに消滅していく路面のタイヤ痕や落下物、ガードレールや信号機などの道路施設の損傷など交通事故の証拠を保全するためです。
加入している任意保険会社を確認
交通事故の相手がどこの任意保険会社へ加入しているか確認します。
このとき、代理店や担当者などを確認できなくても、後日、相手が加入している保険会社の担当者から詳細を確認することができるため、交通事故現場において詳細な情報までは必要としません。
ただ、交通事故の相手が加入している保険会社は「○×海上火災保険株式会社」であると知っていれば、後日、保険会社からの連絡に慌てず対応できます。
保険会社への連絡
任意保険に加入している場合、交通事故が発生したことを告げ、相手の情報や負傷の程度、緊急搬送される病院名などを担当者に伝えます。
交通事故が夜間に発生した場合や休日に発生した場合など保険会社へ連絡できないときは、加入保険会社の営業時間に交通事故が発生した旨の報告を改めておこないます。
交通事故が発生してから60日以内に加入している任意保険会社に対し事故報告をおこなわなかった場合、原則として保険金は支払わないと定めている任意保険会社が多数あるので注意が必要です。
絶対にしてはならないこと
実際に交通事故現場で体験した事例
以前、交通事故とは別の依頼を頂いたお客さま(以下、「お客さま」といいます。)から急に呼び出され、指定された場所へ慌てて駆け付けたところ、そこは、ある交通事故現場でした。
どうやら、お客さまが運転する車両が交差点を右折する際に左側に膨らみ、交差点を直進しようとした相手方車両の右側前方に接触した交通事故ということでした。
お客さまは、知人の言葉「交通事故現場では謝罪せずに保険会社へ一任すると答えると良い」を思い出し謝罪要求に応じていませんでしたが、相手からの度重なる謝罪要求に耐え切れなくなり私に謝罪すべきかどうか尋ねてきました。
双方が交差点内を移動しており、どちらかの一方が原因で発生した交通事故と断言できないことを理由に、交通事故の責任についての謝罪はできないため、時間を要する事故処理により相手に迷惑をかけた事実について謝罪するようにお答えしたところ・・・
それまで謝罪要求を繰り返してきた相手は一変し、当該交通事故の原因となったお客さまが全責任を負うといった内容の念書を作成するよう要求し始めました。
お客さまに、事故処理に時間を費やすこととなったことについて謝罪しても構わないが、絶対に念書の作成に応じてはいけない旨を伝え、相手の情報を収集してその場を解散させました。
交通事故現場では誤ってはいけない?
事例のお客さまに限らず、交通事故現場では相手に謝罪しない方が良いとされている理由について、少し考えてみます。
本来、自身の行為により他人に危害や損害を与えたときまたは迷惑をかけたとき、先ずは謝罪すべきです。
なぜ、交通事故現場においては、自身に落ち度があっても謝罪しない方が良いのでしょうか?
事例のお客さまは、知人から次のようなことを聞いたと教えてくださいました。
交通事故現場で謝罪すると、次のような流れで手続きが進行する
- 交通事故現場で相手に謝罪する
- 相手は優位な立場になったと勘違いする
(自身が不利な立場となる) - 過失割合に影響する
- 賠償や補償の面で不利になる
知人から聞いた交通事故の流れ3つ目にある「過失割合に影響する」ですが、まずは過失割合についてです。
過失割合は、加害者側から提示して被害者側と示談交渉の場において定めるもので、交通事故現場で当事者同士または警察官が定めるものではありません。
過失割合は、警察によって作成された実況見分調書を参考にして交通事故の状況を確認し、過去の裁判例を踏まえて示談交渉によって定められます。
当然、示談交渉の場において加害者の言い分と被害者の言い分が衝突すれば紛争手続きへと発展します。
交通事故現場で相手からの謝罪を受けた当事者の一方は、原因が相手にある交通事故だから自身は何も悪くないと考えてしまうことが多く、自身の落ち度について任意保険会社に伝えることはあまりありません。
加入者自身の落ち度について知らない任意保険会社は、加入者の過失がない(少ない)交通事故として、加入者の過失を低く主張することがあります。
相手方任意保険会社からの不条理な過失の設定に納得できない場合、その主張を覆すためには一般的な法律知識だけではなく、交通事故に関する専門的な知識が必要なため、専門家へ依頼することとなり、自身で示談交渉を継続することが困難となります。
示談交渉において、不利な過失割合を覆すことができなかった者によって、「交通事故現場では相手に謝罪しない方が良い」と語り継がれてきたのではないでしょうか。
絶対にしてはならないこと
交通事故の発生により加害者または被害者となったとき、たとえ交通事故の相手から求められた場合であっても、絶対に以下のような要求に従ってはいけません。
損害賠償や示談に応じる要求
交通事故による損傷が軽い物損であれば、その場における当事者の話し合い(示談)により解決することがあります。
人身事故において、その場で要求された損害賠償や示談に応じる要求を受け入れた後、後遺症が残った場合や過失割合などによって、示談後に支払われる後遺障害慰謝料や逸失利益などの金額が大きく変わった場合であっても、一度成立した示談を後発の事由を理由に改めてやり直すことはとても大変です。
交通事故現場で相手から損害賠償や示談を強要された場合であっても、その場で応じることのないようにしましょう。
念書を作成する要求
交通事故の加害者となり、たとえ交通事故の相手から要求または強要された場合であっても、絶対に加害者が交通事故のすべての責任を負うといった内容の念書を作成してはいけません。
過失割合は、加害者・被害者それぞれの主張や道路状況、過去におこなわれた裁判の結果(判例)や交通事故発生時の周辺の環境などを総合的に判断して示談交渉によって決めるものです。
念書を作成した後、現場検証などにより自身の正当性を主張できる状況であったことが判明した場合であっても、念書の存在を理由に自身の正当性を主張することは非常に難しくなってしまいます。
交通事故の当事者が非日常的な交通事故現場において動揺してしまい、相手から要求または強要された内容に従ってしまうことがあります。
交通事故現場では、普段以上に落ち着いた行動を心がけるようお願いいたします。
交通事故に強い専門家とは
交通事故に関する業務について専門的に取り扱っていない場合、交通事故について、詳しくなくても仕方のないことかもしれません。
職種を問わず交通事故を取り扱える専門家だと語る者であったとしても、交通事故により受傷した損傷が惹き起こす症状や病態について精通しているとも限りません。
交通事故当初から他覚的所見やあなたが訴える症状をもとに適切な後遺障害の等級認定を見据えた治療法や検査の実施および自賠責(共済)保険のしくみなどについて説明もしくは提案できる者こそが交通事故を取り扱う専門家だと考えています。
たとえ敏腕弁護士であっても自賠責(共済)保険が判断する後遺障害に該当しなければ、その後の示談交渉や裁判手続きにおいて納得できる結果を導き出すことはとても難しいです。
ウェーブ行政書士事務所では、あなたの利益を最大限確保するための適正な後遺障害の等級認定の取得を第一の目標としています。
示談交渉や裁判上の手続きがあなたにとって、有利な結果を導くこととなる後遺障害の認定に向け、全力であなたやあなたのご家族をサポートいたします。
後遺障害の等級認定申請の代行が完了した後の手続きについては、ウェーブ行政書士事務所の理念に賛同いただいている弁護士があなたを全力でサポートいたします。
ウェーブ行政書士事務所へご依頼いただいたあなたは、交通事故に関する問題が解決するまでの期間において自身の治療に専念いただくこととなり、示談終了後に必要となる治療費や後遺症による収入減少といった金銭的な不安から解放されることとなります。
.png)
.png)




保険.jpg)